【個人事業主】事業主貸とは?多用しないほうが無駄が少ない理由

筆者はやよいの青色申告を用いて普段の仕訳を行っていますが、個人事業主になったばかりの頃は不要な仕訳を大量に入力してしまっており、とても時間がかかっていました。不要な仕訳には主に「事業主貸」の勘定科目が関連していたので、この失敗談を解説したいと思います。
事業主貸について触れる前に
個人事業主とは
今回の記事を語る前に個人事業主の解釈を整理します。
個人事業主とは、開業届を税務署に提出した事業を営む個人のことです。
開業した事業の主、ということで個人事業主です。
「事業」と「個人」
開業届の提出によって生まれた「事業」、その主となる「個人」ですが、仕訳上ではそれぞれを別人格として扱います。
別人格として扱うにあたり、銀行口座やクレジットカード、財布、Suica等、入出金のある媒体に対して「事業用」なのか「個人用」なのかを定義付けします。
ただし、この定義付けは事前申告などは無いので好きに決めてOK、いつ変更してもOKです。
下記の記事では、銀行口座、クレジットカードを「事業用」と「個人用」に定義付けした場合の仕訳の違いを記載したので、よかったらご参考ください。
事業主貸とは
事業者が個人事業主にお金を貸すこと
事業者と個人事業主、どちらも自分なので一見お金の貸し借りがあるようには見えませんが、前述の「事業用」「個人用」の定義付けの話を踏まえると説明できます。
例えば、事業用に定義した銀行口座のお金(1万円)を個人用に定義した銀行口座に移した場合、事業主貸を用いた仕訳が発生します。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
| 事業主貸 | 10,000 | 普通預金 | 10,000 |
他には事業用のクレジットカードで個人の生活用品を購入する等、事業に関係の無い支出は全て事業主貸を用いて仕訳します。
事業主貸を使用した失敗例
筆者は事業で得た売上の一部を送金し、iDeCoやNISAの積立だけを行っている銀行口座を持っていますが、これらの取引を全て仕訳していました。
(事業関連の取引が無いにも関わらず、事業用の銀行口座として定義付けしていたため)
例えば、iDeCoで65,000円分の投資信託を購入した際の仕訳は次の通りです。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 | 摘要 |
| 事業主貸 | 65,000 | 普通預金 | 65,000 | 〇月分_iDeCo |
この銀行口座が他に事業に関連する取引を行っていて、事業用の銀行口座として使用しているのであれば上記の仕訳も必要ですが、そうでない場合は不要です。個人用の銀行口座として定義付けすれば仕訳しなくてOKです。
また、個人用の銀行口座でもし仮に事業関連の取引があったとしても、事業主借の勘定科目を用いることで仕訳できます。
なんでも事業用にしない
事業用に定義したカードや銀行口座で発生した取引は全て仕訳しないといけなくなるため、基本的に個人用に定義し、必要に応じて事業用に定義するやり方が仕訳を増やさないコツになります。
逆に全て個人用に定義すると、事業関連の取引に事業主借の勘定科目を用いることになりますが、売上を誤魔化すような使い方をしなければ問題ありません。
事業主貸(事業主借も)を正しく理解して利用することが普段の仕訳を簡単にすることにつながるので、個人事業主になりたての方はしっかり学んでおくことをおすすめします。

 https://pecorimaru.com/business-or-private/
https://pecorimaru.com/business-or-private/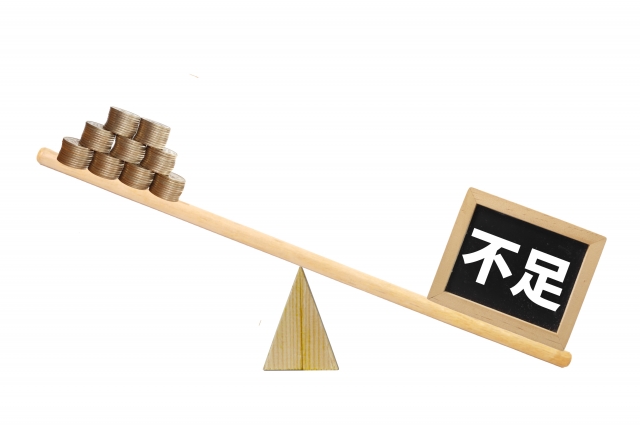





ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません